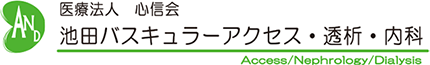シャント外来について
シャント外来では、シャントの抱える問題(狭窄・閉塞・瘤/コブ・感染・疼痛)の診察・診断・治療を行います。
血管アクセス(透析シャント)のトラブルをガイドラインに従って解決し、長期開存を新規シャント作製段階・再建から考えます。
また当院では、当院以外の患者様でもシャントの治療や手術・手術後の管理・定期的な検査を受けていただきシャントの管理に積極的に取り組んでいます。
外来相談へは、電話予約・インターネット予約にておいで下さい。
- 当院では全てのシャント手術を局所麻酔で行っています。
- 基本的には日帰りで行いますが、出血の程度により安全のため一泊入院を勧める事もあります。
手術
バスキュラーアクセスに関する様々な手術に対応しております。

- シャント作製術・修復術
- 人工血管留置術
- シャント瘤除去術
- シャント血流コントロール術
- 動脈表在化手術
- 動脈、静脈直接穿刺
- カフ付きカテーテル挿入術
- シャント閉塞時血栓除去術
当院で行うシャント手術の特徴
経験豊富な医師が執刀いたします
当院のシャント作製、再建術は、ガイドライン作成に携わった医師(院長)が、責任を持って行います。
シャント作製・再建手術は、約3,500例以上の実績がございます。
外来シャントPTA、日帰りシャント作製、人工血管留置術(近医への入院可能)、長期留置カテーテル挿入等を行なっております。
日帰りが可能です
シャント手術は基本的には日帰りで行なっております。
ご遠方からお越しの患者さん、ご希望の患者さんには近医への入院が可能です。
最新型モバイル血管撮影装置を導入しています
当院では、より正確な診断と低侵襲治療を目的として、頭部から四肢まで全身に対応する最新型モバイル血管撮影装置を導入いたしました。
造影剤アレルギーの患者さんに対応したエコー下PTAを実施。
傷をより目立たないように処置しています
シャント手術の傷(皮膚縫合)は手首周辺に残り、半そでを着る季節になると特に目立ってしまうケースが多々あります。
血液透析ができることを優先するため、皮膚縫合の美しさを要求されることはこれまでは滅多にありませんでした。
当院ではシャント手術における皮膚縫合の美しさにもこだわり、形成外科的な技術を取り入れ、傷をより目立たないように処置しています。
通常のシャントはもちろん、作り直しや瘤の手術の時も同様に処置しています。
基本的に日帰り手術を行うのも特徴のひとつです。
- メールでの御相談も受け付けています。
- 外来受診の際はWEB・電話にて予約されご来院下さい。
手術までの流れ
手術当日・術後の流れ
※必要時入院
(翌日)
(創部処置)
(抜糸)
手術以外の治療方法

経皮的血管形成術(PTA)
様々な原因でシャントは狭くなったり、閉塞したりします。
手術を行うのではなく、カテーテルを使用して血管を内側から押し広げ血行を再建する治療方法があります。
それを経皮的血管形成術(PTA)といいます。
当院ではPTAを施行する前後にエコー検査を行っています。
血流量やRI値などを測定しPTAを行う時期を決めていきます。
定期的にエコー検査に来られ、狭くなっている時にのみPTAを行って帰られる患者さんもいらっしゃいます。
PTAとなれば手術室に案内します。
PTAが終了し止血ができたら、再度エコー検査にてどの程度改善しているかを確認します。
エコー検査が終われば帰宅となります。

長期留置カテーテル術
透析をするためには、たくさんの血液を体の外に取り出すことが必要です。
一般的には腕の血管を手術してバスキュラーアクセス(シャント血管)を作りますが、何らかの原因でシャントを作ることが難しい場合に、シャントに変わり長期に使用できる留置カテーテルとして「ショーンカテーテル(写真1)」が選択されます。
血液を取り出す側(動脈側)赤の管と、血液を体に戻す側(静脈側)青の管がそれぞれ1本ずつあります。
透析をおこなう場合の針刺し(穿刺)はなくなりますが、鎖骨の下の前胸部から管が出ているので、最低限の管理が必要になってきます。
利点
- 針を刺される痛みがない
- 針を抜いたときの止血がなくなる
- 透析中両手が使える
- 心臓への負担が少ない
欠点
- 24時間カテーテルが入っているため、日常生活に多少の制限がある
- カテーテルという異物を体内に入れているので、細菌感染を起こす可能性がある
細菌感染を起こさないためには?
濡れたテープやガーゼはすぐにはずし、出口部の消毒をし、きれいなガーゼを当てましょう!
(汗や水などで濡れたままにしていると感染の原因になります。消毒方法が分からないときには病院に連絡してください)
お風呂は、細菌感染の原因にもなるため、防水処置をして入浴となります。
一番風呂が望ましく、汗で防水処置が剥がれないように注意して下さい。
- 痛みや熱・かゆみが出てきた場合は病院に連絡するようにしましょう。
- Q. 手術をしてどのくらいで使用できますか?
- 手術をした当日から使用できます。
しかし、手術直後は皮膚の下に入れたばかりなのでカテーテルと皮下の組織が不安定な状態です。
感染の可能性があります。
皮膚の状態によっては1~2週間は、かゆみ等の違和感がある方もいますが、2~3日でほとんどの場合はスムーズに透析へ移行できています。
基本的には日帰りでおこなっており術後は自宅に帰れます。 - Q. 長期留置カテーテルは、体のどこに入っている?
- カテーテルは、内頚静脈(首の血管)から入っており、カテーテル先端は心臓の右心房にあります。
カテーテルが体の中から表面に出てくる部分を出口部と言います。
出口部までは皮下に埋没した状態で外から見えることはありません。
出口部以降が体表に出ている状態となります。
長期留置カテーテル手術の流れ
手術前
- 主治医より手術の方法、必要性、目的などについての説明があります。
- 来院時間は手術予定の2時間前に来てください。検査や点滴の準備などがあります。
- ワーファリン等(血液をさらさらにする薬)を飲まれている方は主治医の指示で手術まで服用を中断することがあります。その場合は手術後指示があるまでは服用しないようにしてください。
手術当日
- 手術は局所麻酔で行いますが、必要に応じて静脈麻酔も使用することもあるので、昼食は摂取しないようにしましょう(朝食はしっかり食べてきてください)
- 来院されたら、まず受付で手続きがあります。その後リカバリルームに案内します。
- リカバリルームでは、手術用の衣に着替えていただきます。
- レントゲン・心電図・エコーの検査があります。それらが終わったら、採血と手術の為の点滴をします。
- 手術までの時間をリカバリルームで待っていただきます。その間に、排尿と排便はすませてください。
- 手術は約30分です。
- 手術が終わったら食事は召し上がれます。手術の後は先生の指示があるまでリカバリルームで休んでいただきます。
- 出血が多く安静が必要な方、患者さんの希望がある場合は他の病院に入院することが出来ます。
手術後
- 手術の当日から、長期留置カテーテルでの透析が可能となります。
- 処置はしばらく病院にて行います。出血や膿などでガーゼ汚染したり、痛みやかゆみが出現した場合は、病院まで連絡をください。
- 長期留置カテーテルが体内で安定するまで1ヶ月かかります。それまでは日常生活で首やカテーテル留置している側の腕を激しく動かさないようにしましょう。
- カテーテルの管理については、看護師より指導があります。介助が必要な場合は、介助の方にご協力をお願いすることもあります。
日常生活での注意点・観察ポイント
注意点
- カテーテルを引っ張ったり、曲げたりしないでください。
- 濡れたり、汚れたりしたときは病院に連絡してください。
- 首やカテーテル留置側を激しく動かさないようにしましょう。
- 透析日は、前開きの下着やパジャマが好ましいです。
- 首が開いた服を着る場合には、スカーフなどをした方が留置部はかくれます。
- お風呂は一番風呂が望ましく、防水処置をして入浴されてください。
- 汗で防水処置が剥がれないように注意してください。
- 就寝時には、カテーテルの折れ曲がりや引っかかりに注意してください。
観察ポイント
- 皮膚の状態の確認(出血の有無・かゆみ・発赤・痛みなど)
- カテーテルを引っ張っていないか、明らかに抜けてきていないか
- カテーテルに傷はついていないか
- 固定のテープははがれていないか
上記の観察ポイントを確認の上、異常があれば速やかに病院へ御連絡ください。
入院施設
入院が必要な場合、また、入院をご希望の患者さんに関しては、連携している病院を紹介させていただきます。
- 担当の看護師が病院まで付き添います。